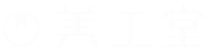武将たちの休息術、一服のお茶がもたらす和み
会津と茶湯の物語に光を当てた今年3年目の企画「Aizu Tea Storries」が鶴ヶ城や市内各所で始まります。そんな時期なので利休七哲の筆頭ともされた氏郷公とお茶のエピソードを紹介します。
文禄の役(1592~93年)の最中、肥前名護屋城で戦果の報告を待つ豊臣秀吉は、付近にある瓜畑に旅籠や店を建て、街並みを再現させて「やつし比べ」を催したそうです。今でいう仮装大会。
前田利家は仏具を入れる木箱を担いで高野聖(こうやひじり)を演じ、徳川家康は「あじか」と呼ばれるザル売りに、そして秀吉は瓜売りになって菅笠と腰蓑姿で籠を担ぎ「味良しの瓜、めされ候え」と売り声をかけ歩いたといいます。
そんな中の氏郷公。城下にいる一服一銭(野点屋台)の茶売りに扮し、担ぎ屋台で秀吉に茶を点ててふるまったそうです。
誰それは愉快、あ奴はつまらん、など笑いや批評を集めながら、なぜか出世している大名ほど芝居が巧かったようです。氏郷公も流石。しかし戦の最中に家臣に心の余裕を持たせる秀吉、それに本気で応える家臣たち。和みます。